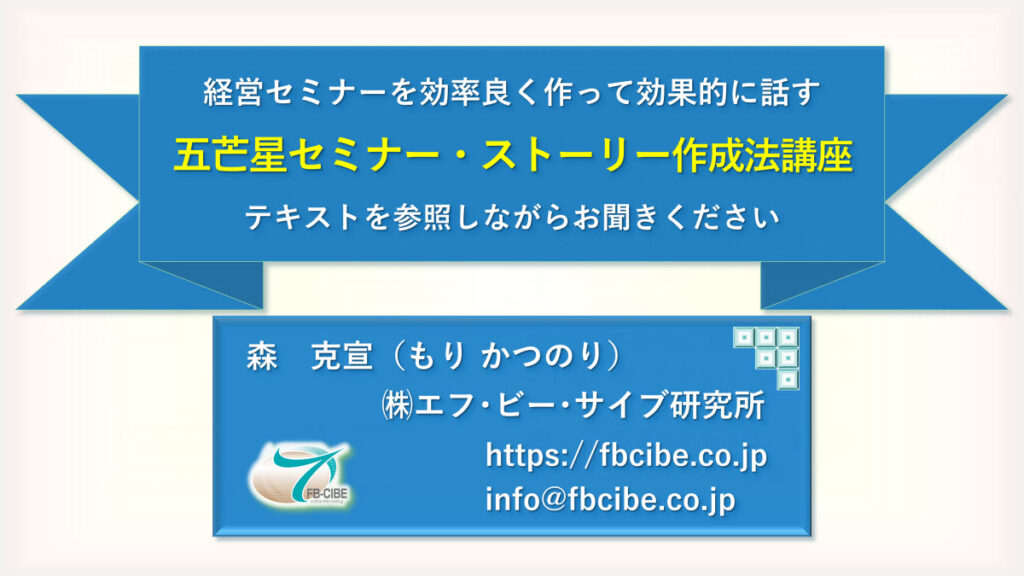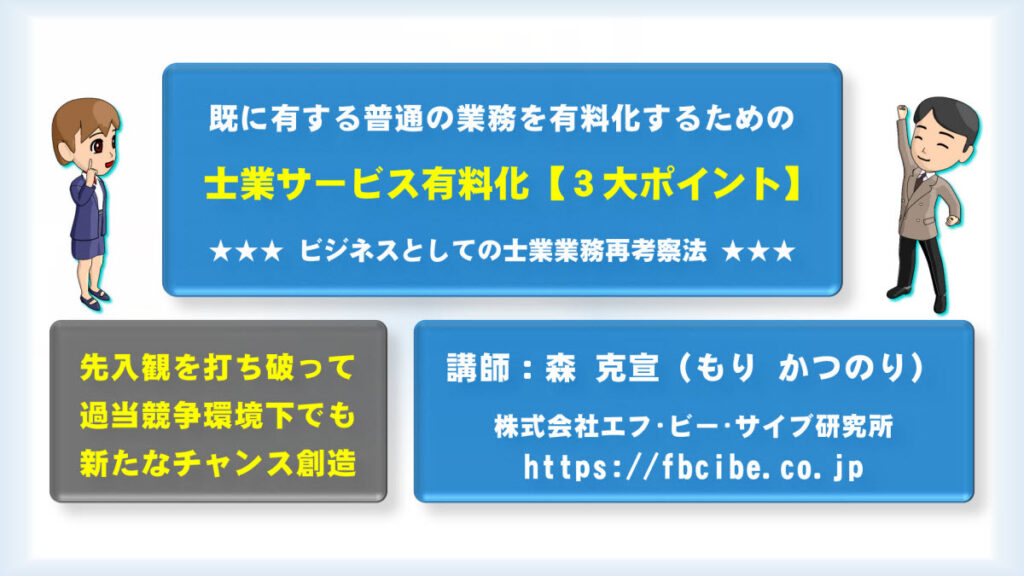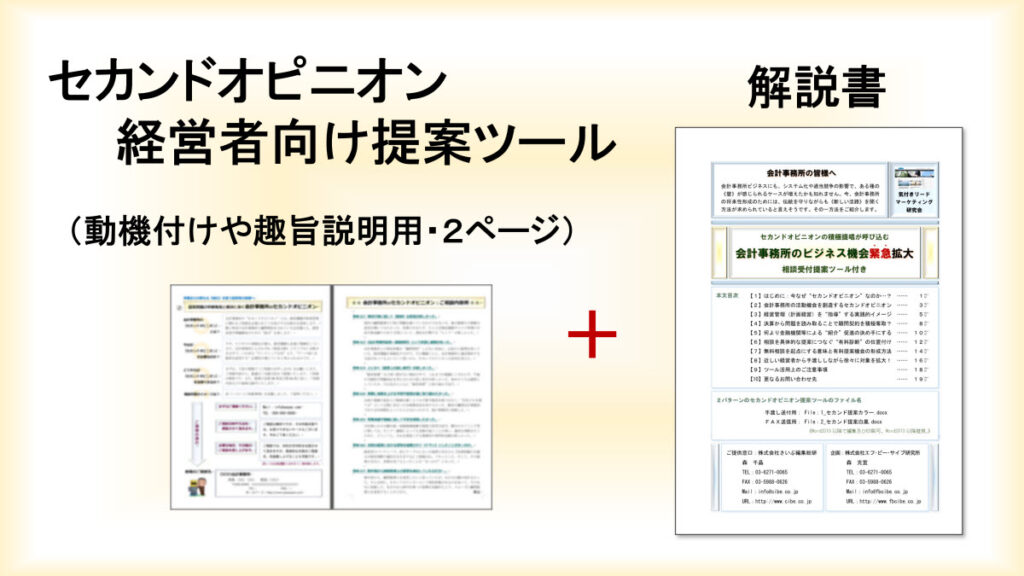会計事務所にとっても、経営者向けのセミナーが持つ意味が大きく変わって来ています。それは《どのような変化》で、《どんな効用》が新たに生まれるのでしょうか。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.セミナーによるブランド形成の意味低下?
士業ビジネスにとって、経営者向けセミナーには一種のブランド効果があったと言えるでしょう。それは申し上げるまでもなく、そこで生まれたブランドが、その後の紹介に繋がりやすかったからです。
紹介が得られない場合も、セミナー講師の《印象》は、顧問契約提案に際する《後押し》要因になってくれました。
2.実利に乏しくなった経営者向けセミナー
ただ現在では、セミナー主催者から受ける《紹介》には、問題企業の経営革新等のケースが増え、顧問契約どころか、スポット契約でも《魅力》に乏しい案件が増える傾向にあります。その一方で、スタートアップ企業との顧問契約は、非常に厳しい競争が待ち受けているのが普通です。
その上、中堅中小企業市場が《飽和》状態へと進み、顧問契約自体の獲得チャンスが小さくなるにつれ、《経営者向けセミナー》は、存在意義を失ったかにさえ見えてしまうのです。
3.コンサルティングにも新たな側面が浮上?
ところが、そうした従来型のセミナーに陰りが見え始める一方で、中堅中手企業へのコンサルティングの在り方にも、大きな変化が見え始めました。
それは、そもそもMAS(会計事務所のコンサルティング)とは、過去経営に対する未来経営法、つまり計画経営を《支援・指導》するものでしたが、企業の多くにとって、その《未来経営》の意義を感じ取るのが難しいからです。意義を感じ取れても、自社に適合するとは思えないケースも少なくないでしょう。
4.MASに至るまでの準備段階のビジネス化
つまり、かつてパソコンを業務に使うイメージを持てなかった経営者に、その活用イメージを持たせて『一度、簡単なことから試してみよう』というアプローチが盛んだったように、今『未来経営法を、こんな身近なところから試してみませんか。そうすると、資金繰りの限界を破る方法も見つけやすくなりますよ』という類の《動機付け》から始める必要があるということです。
5.たとえば資金繰りに振り回される企業で…
たとえば『目前の資金繰りに振り回されている我が社に、予算を作る暇などない』と感じている経営者がいるとします。その経営者に『超概算でも、予算を作る習慣が身に付けば、先行きの資金収支管理の精度が上がって、少なくとも振り回されなくなりますよ』と指摘すると、どうでしょうか。
しかも《超概算の予算》は、前年の月次試算表の数値を《当年度の予想》として置き換えてみるだけでも、ある程度《意味のある形》になるものですと、伝えるのです。
6.取り組みが容易な方法から段階的指導開始
そして《予算作成》とは呼ばず、『12ヵ月分の試算表結果を、当年度の超概算予想に置き換え、資金収支の超概算見通しを作る方法の習得を試してみませんか』と誘います。
『それは、1日か2日でできることですし、分からないことは(パソコンのサポートのように)一定期間ご支援します』と、そういう方式が、現代の経営者には必要なコンサルティングだと捉え直してみるのです。
7.経営自体のコンサルティングは危険を伴う
そうすると面白いことに、『未来経営の指導などを行っていたら、責任重大で大変なことになっていた』という気さえして来ます。そもそも『貴社の事業はこうあるべきです』等という指導ができたのでしょうか。
そんな風に捉えると、言い過ぎ覚悟で申し上げるなら、MASあるいは計画経営が中堅中小企業に《あまり普及しなかった》のは、それが企業にとって高度過ぎる手法で、会計事務所にとって危険すぎる方法だったからだとも思えて来るのです。
8.未来経営法の普及に勢いが出なかった背景
ただし、そうならざるを得なかった背景には、経営者に《これならできる》と動機付ける《セミナーや勉強会のストーリー》が作りにくかったことと、多様なレベルの経営者に《有料》指導を提案する技術が確立されていなかったことが挙げられるかも知れません。
付加価値を充実させた顧問契約で稼ぐという従来のスタイルが、会計事務所のビジネスチャンスに壁を作っていただけではなく、今日の企業に必要な《未来志向を現実のプランにする技能》の普及の重荷になっていたとするなら…。
9.今経営に求められる自分流に取り組む姿勢
では、どうすべきなのでしょうか。その回答の方向性が、《①経営者を動機付ける話の作り方》と《②経営者の現実に合わせた実務指導を有料化する方法》を、会計事務所が見つけ出すことにあると言えそうなのです。
上記の①と②は、会計事務所の本業に比べて、難しいものでも高度なものでもありません。ただ《知っているかどうか》で決めまるもの、すなわち《ノウハウ》だと捉え得るものです。
10.動機付けセミナーの作り方を今風に大改訂
2010年に《セミナーの作り方とサンプルストーリー》の講座を作成し、一定の評価を頂きました。しかし、その内容は上記の《ブランド形成》型セミナーの域を出るものではありませんでした。もちろん、域を出る必要がなかったからです。
やや言い過ぎの面はあっても、上記のような環境にある今日、その講座を抜本的に作り直し、もう1つの《業務有料化講座》と合わせて、《①動機付け》と《②有料化》の方法をご紹介することといたしました。
11.セカンドオピニオンの形態からの取り組み
スポット契約的ではあっても経営者支援を有料化すれば、企業に実践力が付くまで一定の期間、サポートを継続的できます。同時に、現在の《先を見る余裕》さえない状況から経営者が抜け出したいと考える時、《思考の代行=判断の選択肢作り》を、一定期間の費用(投資)の対価として得られることが、経営者にも理解しやすくなるのです。
顧問契約では、サポートが延々と続くだけではなく、その都度《相談》を持ち掛けなければ《回答》が得られません。つまり《自分だけで考える》ことが強いられるのです。それでは経営者が『自分にも取り組めそうだ』とは感じにくいでしょう。
会計事務所が持つ見識を経営者が学び取るためには《終点が明確な時間=スポット契約》が必要なのです。ただ、既に定着している顧問契約体制の下では、顧問先の動機付けは簡単ではないかも知れません。そのため今後は更に、《セカンドオピニオン体制+スポット契約への動機付け》を《視野に入れる必要性が高まる》と思われるのです。