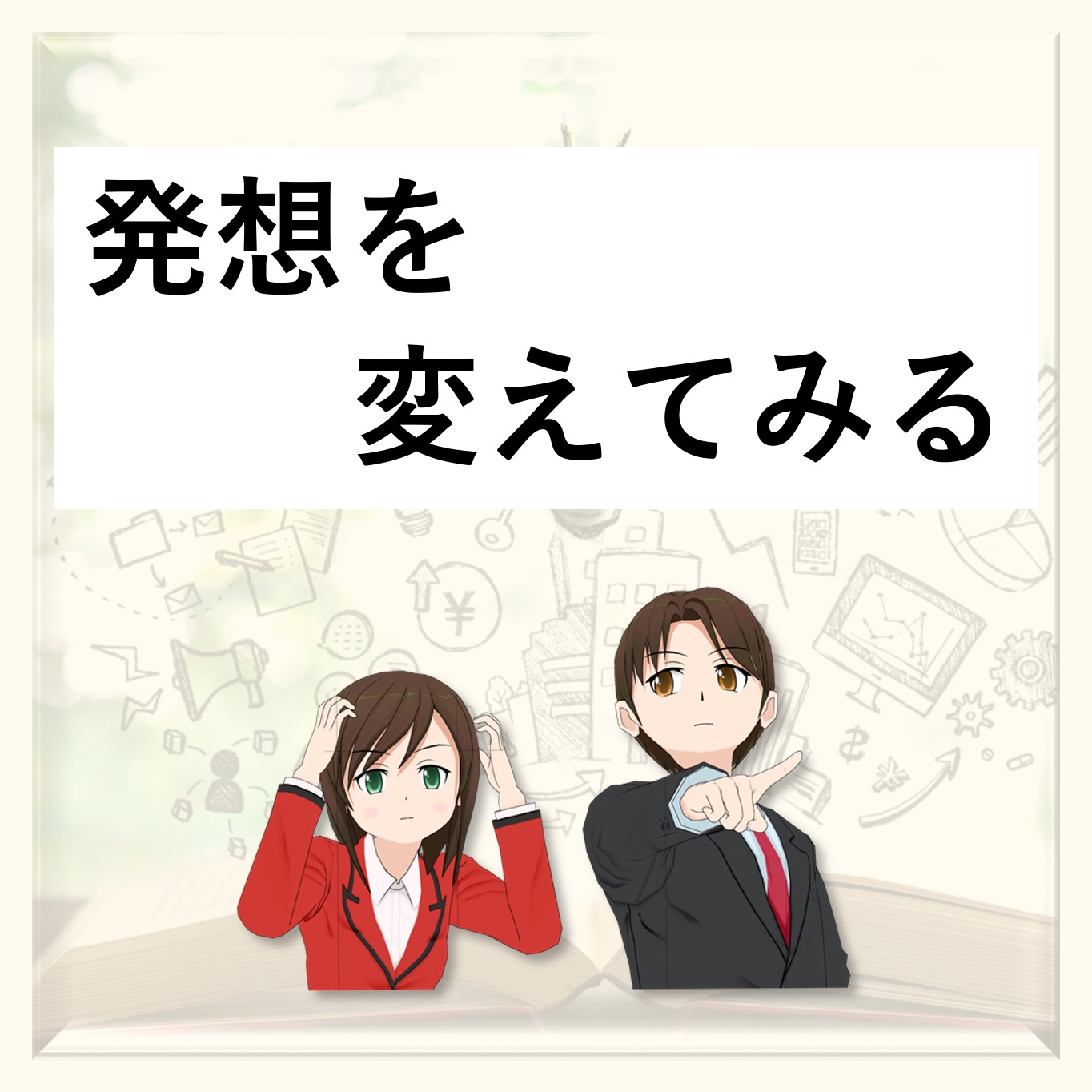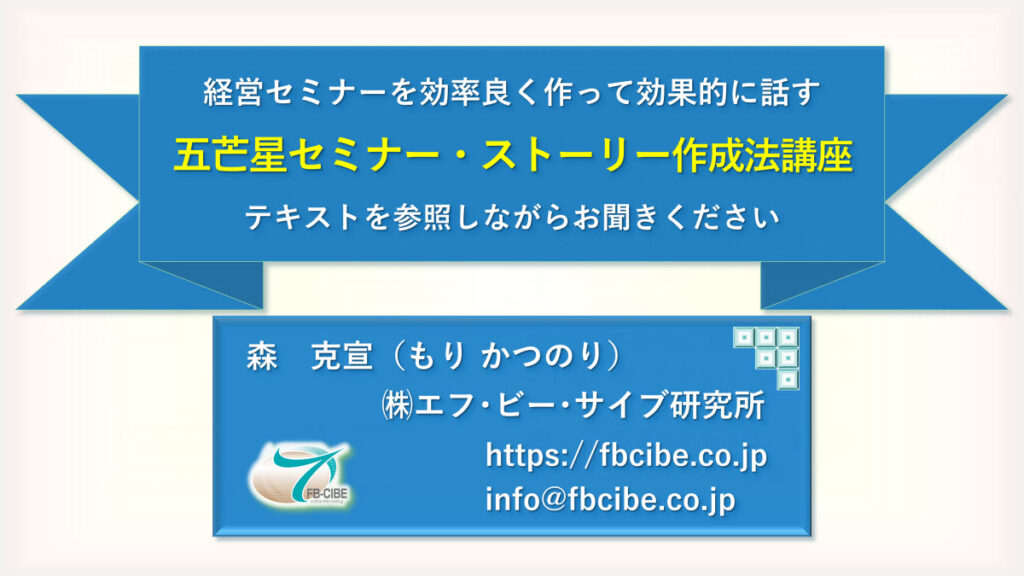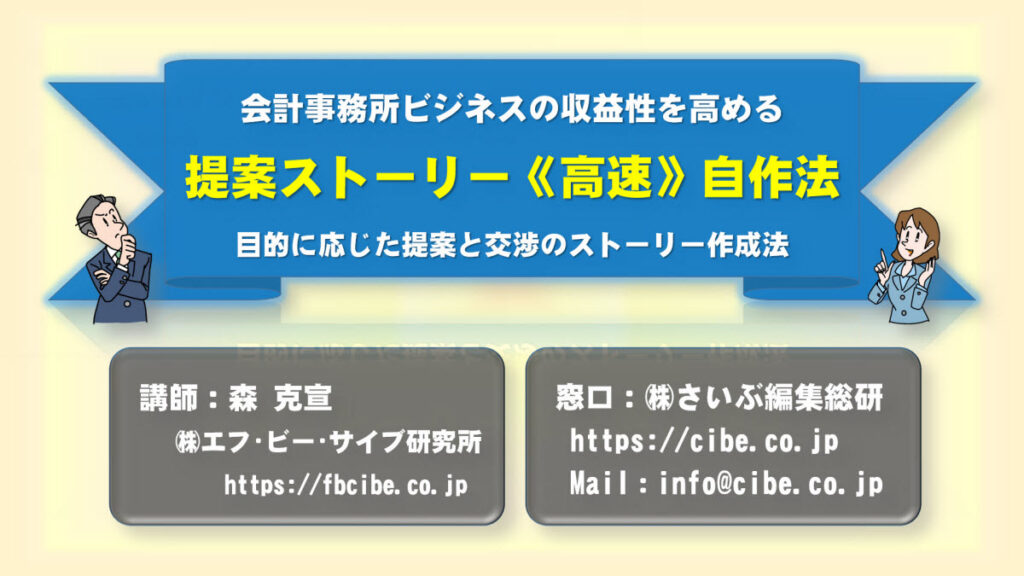(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
今回は、以下の本文を《生成AI:GoogleNotebookLM》で、2人の対話形式で解説した音声をも添付しています。
ぜひ本文と比較しながら、《生成AI》の力を、ご検証いただきたいと思います。音声は可能な限り編集していますが、発音間違い等はシステム上一部残っています。
1.次の一歩を絞り込みにくい環境
『今後どうすべきか』を考えれば考える程、手詰まりに思える時があります。今、そんな感覚に陥るほどに、次の一手が絞り込みにくい“事業環境”にあるのでしょう。
しかもそれは、成長企業でも苦境にある企業でも、内容こそ違え、状況としては同様だとも言えそうなのです。会計事務所の先生方も、例外ではないかも知れません。
2.視線の方向転換が活路を開く?
そんな時、『なぜこんなことになったのか』と、理由を分析することも大事ではありますが、視線の先を《自社や自分自身》に変えて、『今、何ならできるのだろうか』と捉え直してみると、意外な活路を開きやすくなるケースが出て来るようです。
しかもその意外な活路は、連鎖反応を起こすこともあり得るのです。たとえば、ある製造業A社が自社製品の《オーバースペック》面を見直せば《価格の引き下げ》ができることを発見したとします。すると、その製品が、今度は直接の取引先B社の製品仕様上の迷いを払拭させて、製造上の生産性を高めさせ、自社の利益アップの道を見出させることがあり得るからです。
3.会計事務所が起こせる連鎖反応
企業間の《連鎖反応》に、会計事務所が関与するのは難しいでしょう。しかし、会計事務所を起点とする《連鎖》は起こせそうなのです。そして、その連鎖は先生方が、まず『自事務所に今、どんな経営支援であれば《すぐに》でもできるのか』と、考えてみるところから始まります。
たとえば、ある事務所では先生が『今できることは、せいぜい資金収支管理の助言くらいだろうか』と言われていました。特に、運転資金をショートさせないための《アドバイス》に、長年取り組んでおられるからです。
4.重荷になる難題に取り組むより
その先生が、資金収支管理のサポートから一歩進んで『その管理法を、経営者や経理担当者に教えることは難しいだろうか』と捉え直してみるのです。もちろん収支見通しや予算を作る指導は、企業には難題で、先生には重荷かも知れません。
しかし、何度か申し上げている通り『このままの傾向が続けば、3ヵ月先、半年先、1年先はどうなるか』について、前年の月次情報を参照しながら《いくつかのパターンを作りながら概算想定を試みる》のなら、そんなに難しく考える必要はないでしょう。
5.経営者が自らできることを実感
その《パターン別超概算による想定試算方法》を有料化できなくても、経営者や経理担当者の《意識》は、変わり始めるかも知れません。それは経営者が、『業績数値のことは会計事務所に任せる』のではなく『自社にも“できる”ことがある』と感じ得るケースが出始めるからです。
会計事務所の《できる》が、関与先企業の《できる》の発端になり得ます。そしてその企業が、自社に《できる》ことの発見によって、落ち着きや自信のベースを見出す、あるいは取り戻すなら、事業への取り組み姿勢が変わり始めるはずなのです。
6.それは《どんな》変化なのか?
その変化とは、たとえば《とにもかくにも手持ちの資金を守る》発想から、『たとえ小口でも、投資をしなければ先がなくなる』という感覚への回帰かも知れません。そこには、《経営マインドが少し前向きになる》という効果が生まれているはずです。
その《前向き》発想への回帰は、たとえ資金管理自体の《満足》に至らなくても、『まだ、出来ることが残っている』という《意欲の素》になりそうなのです。経営は、いつの世でも《苦境遭遇と克服》の繰り返しだったからです。
7.簡単な答を探すと見つからない
私たちは今、簡単に《答》が見つかると考えがちな《時代》で活動しているのかも知れません。そのため《すぐに効果が出る方法》ばかりを探し、効果が出なければ、その方法を、簡単に諦めてしまうという傾向を否めないのです。
しかし長い歴史の中では、簡単に答が出る方法は《栄枯盛衰》の波にも簡単に呑み込まれて来ました。その一方で、自分を鼓舞し続ける生き方が好まれ、それによって、自分自身のみならず《社会》が進歩して来たとも言えるのです。
8.《できる》を見出す精神的な効用
そして、その自分を鼓舞する方法こそが、『すべきことではなく、できることを1つでも多く探し出して試してみる』ことに他ならないのです。
そのため、たとえば会計事務所なら《企業のためにできること》を、どんな些細なことでも《リストアップ》してみることが、今肝要だと言えるのです。
もちろん、その《できること》が、企業経営者の何人かには受け入れられなければなりません。つまり《経営者を動機付ける》試みが必要になるのです。そして、その動機付けの試みの1つが、先月ご紹介した『動機付けセミナーストーリーの作り方と話し方』でした。
9.マインド建て直しの向こう側は?
そんなマインド建て直しとも言える活動の向こう側は、期限を切った有料提案、すなわちスポット契約です。
確かに、『スポット契約には継続性がないから魅力がない』とも言えるでしょう。しかし《先行きを見通しにくい》昨今では、継続的な契約は《始める》ことさえ難しいのが現実でしょう。
その意味では、スポット契約を《繋ぐ》方が、今は現実的だとも言えるのです。そして、1つの契約の中で《新たな課題》が見つかる限り、次に進む動機を形成する《動機付け法》が生きて来るはずなのです。
「動機付け型セミナーストーリー」ではなく「動機付け提案ストーリー作成法」については、以下の講座をお勧めします。