1.意図に反して無料サービスを迫られる時
たとえば、顧問先や関与先から『今月大きな損失が発生した。それを前提に、今期の決算と資金収支の見通しを計算して欲しい』と依頼されたとします。そうした相談に、顧問契約の付加価値の範囲内で対処できるなら、それは確かに契約上正当なことでしょう。
しかしその時、先生方の想定以上に手間が大きいのに、その手間が《無料サービス》になってしまうとしたら、その理由を捉えた上で、対処法を考えなければなりません。
2.なぜサービスを《有料》にできないのか?
専門サービスを《有料化》できない理由のほとんどは、実は、先生方が『そのサービスには、これこれの費用が掛かる』と告知していないからに他なりません。そして、告知しない理由には《お金が掛かるとは言いにくい状況》に身を置いてしまうことにあるのです。
《専門サービスの有料化》とは、一口に言うなら、《費用が発生することを告知しやすい》状況を作り出すことにあるのです。
経営者もビジネスマンですから、サービスが無料になるとは思っていません。ただ、無料で押し切れるなら、そうしたいと考えているだけだと捉えるべきでしょう。『へえ、そんなことにもカネをとるの?』と言うのも、威圧によって人を動かすことに慣れた《経営者の常套句》で、特に気にすることはありません。
3.無料サービスも戦略的に実施すべきだが…
ただ、全てのサービスを有料にする必要もないと思います。先生の専門見識で即時対応できるような案件では、いちいち有料化する方が面倒なケースもあるでしょう。
しかし、その際にも『サービス内容と実施方法(=こんなことをこんな風に致しますという告知)と無料サービスの範囲の提示』は必須です。そうしないとキリがなくなるからです。キリが明確でない無料サービスは、先生方の負担になるのみではなく、サービス提供後に『そこまでしかしてくれないのか』という形で、結局顧客の不満の素にもなってしまうのです。
しかも、この『サービス内容の方法と範囲の提示』は、無料サービスの有効性のみではなく、サービスの有料化の基本ともなり得るのです。
4.内容と方法が決まったら価格を設定する
たとえば、先の決算見通しの依頼に際して『状況回復まで3ヶ月かかるとして、その後は予算(あるいは昨年実績)通りに推移するとして計算しますが、いかがですか』と、内容と方法を決めます。
そして『その程度でしたら費用は掛かりません』と言うか、『幾らいくら掛かります』と言うかを決めます。その際、もちろん《納期》の提示も重要になるでしょう。
なお、サービスを無料にするのは、必ずしも企業にとってよいこととは言えません。経営者は『次回も無料になる』と誤解し、何度も依頼を出したくなるからです。取引にケジメがなくなれば、良好な関係も崩れやすくなるでしょう。
どうしても無料にしたい時には、標準価格を提示して無料にするか、次回からは費用が掛かると、一声掛けておくのが取引の鉄則です。
5.目に見えないサービスの価格設定方法
ただ、サービスに価格を付けるのは、想像以上に難しいかも知れません。実際にサービスを提供した時、双方が割高感や割安感を抱くかも知れないという不安が残るからです。
しかし、実のところ、特に専門サービスには適正価格が存在するわけではないと捉えるべきだと言えるのです。専門業は見識提供ビジネスですから、問題は先生方がその価格に満足し、顧客がその価格を受け入れるかどうかという現実の中にあるからです。
6.価格は仮設定と打診の中で決まって行く
そのため、価格設定に関しては、まず先生方が『想定した業務で特に不満はない価格レベル』を想定するところから始まります。そして、顧客の反応を想像しながら価格を調整して、その上で顧客に打診してみるのです。
顧客が高いと思うなら、新たな価格を設定し、再び先生ご自身の満足度に問い掛けます。そうしてお互いの満足の交差点で、契約することになるわけです。どちらかが満足できないなら、サービスは成立しません。あるいは成立させてはいけません。
7.有料化は過剰サービスを断る理由にもなる
条件が合わないからサービスは行わない(行えない)という意識に立つなら、先生方はそれだけで、顧客からの無理難題を制することが容易になるでしょう。無理な仕事は『有料だ』と言えば良いからです。少なくとも、そう言えるような合意関係や契約形態は、今非常に重要になって来ているのです。
一方で、顧客サイドでも『提示された価格が不満足なら、自分で決算見通しを作らなければならない』と感じるはずです。そして、それは自己啓発の機会にもなり、会計事務所の専門性の価値を理解する機会にもなります。
有料化を正面から捉えないために、経営者の自己啓発や専門見識の価値認識の機会を奪っていると考えてみるなら、ビジネス取引が持つ《動機付け機能》に敬意が持てるようになるはずです。ビジネスも営業も、本来は、少なからず建設的なものなのです。
8.実態に即した士業の有料サービスメニュー
もちろん、先の例のような相談対応のみが、会計事務所の有料サービスではありません。計画経営や相続対策や事業承継コンサルティング等、会計事務所サイドから積極的に提案すべき案件の方が、むしろ多いでしょう。
しかし、その場合にも注意が必要です。たとえば、予実管理を提案する時、予実管理の完成形を勧めるばかりが提案ではないからです。経営者としては『今の目標の作り方の問題を知りたい』『予算の必要性を役員会で話して欲しい』『実際、仮予算を作ってみたい』『予実管理の継続的な指導を受けたい』等、様々なニーズを持っているからです。
9.もっと体系的に有料化を捉えるなら…
そのため専門サービスは、たとえば予実管理システムというパッケージを売るのではなく、段階的に経営をレベルアップさせるための階段を、一段ずつ提供するという発想に立つべきでしょう。そして実は、それこそが経営コンサルティングの奥義でもあると言えるかも知れません。
ただ、この話は長くなってしまいますので、別途以下のような講座に、考え方と実践法の両方を、具体的に取りまとめました。


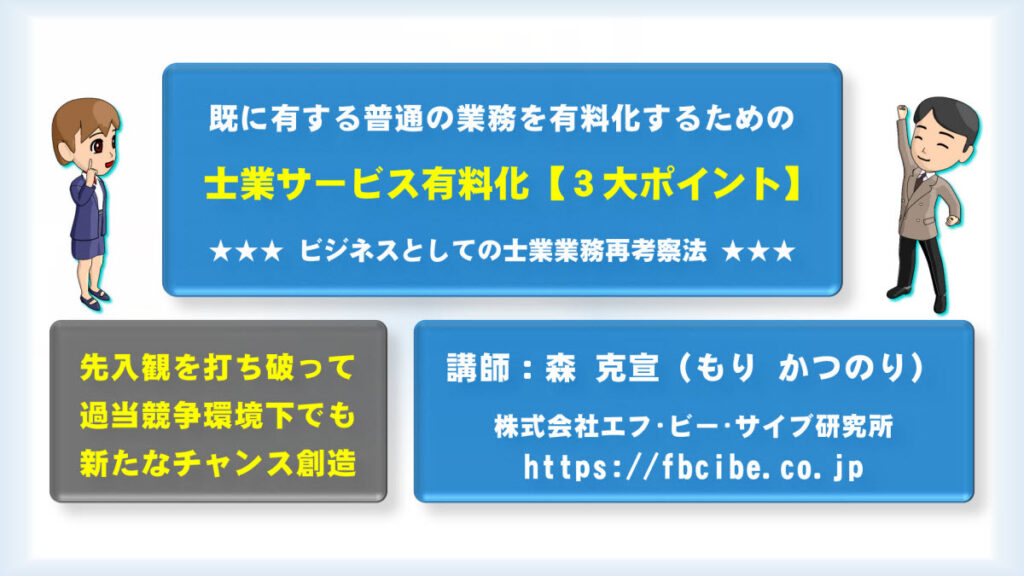
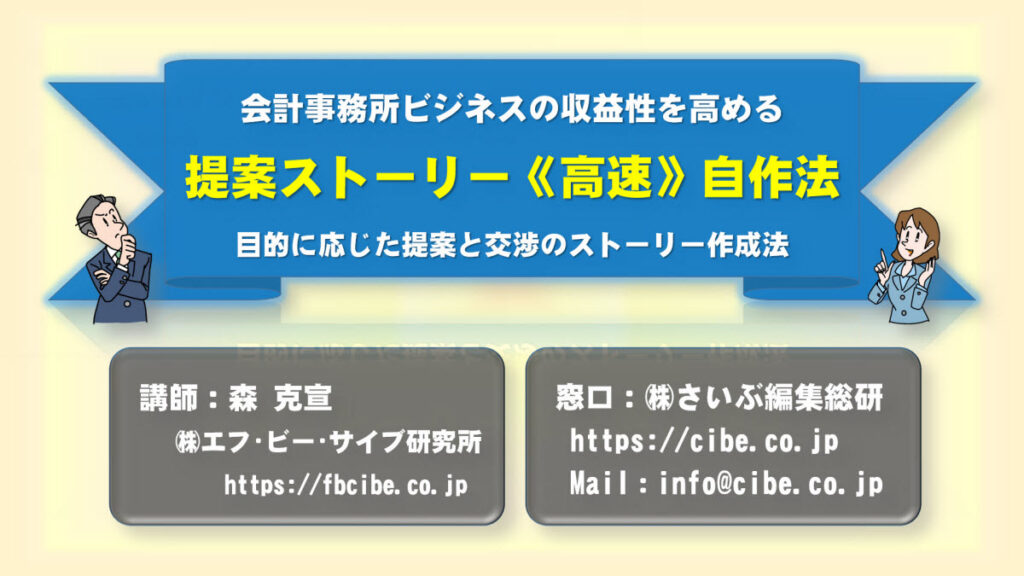
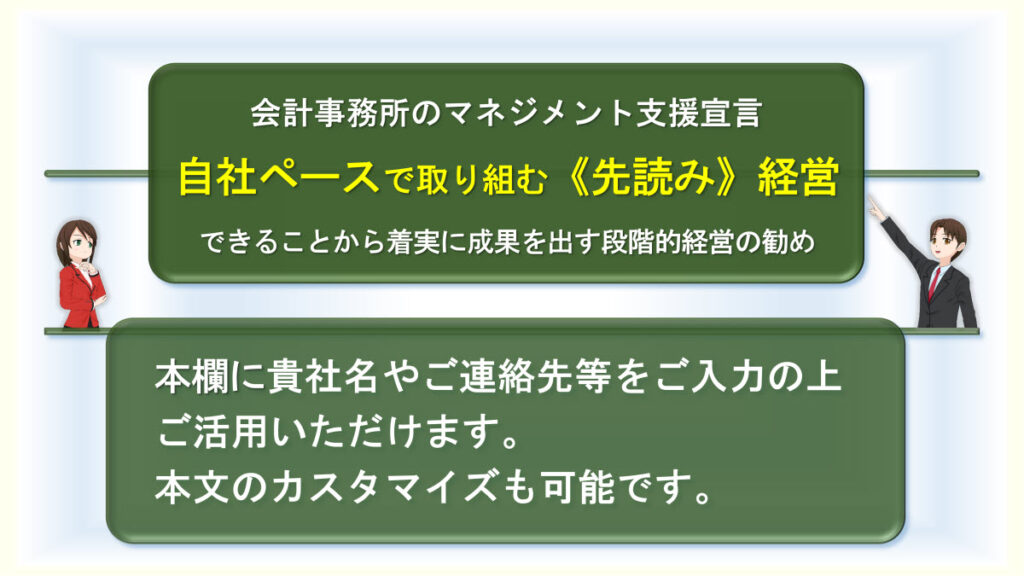
この記事へのトラックバックはありません。