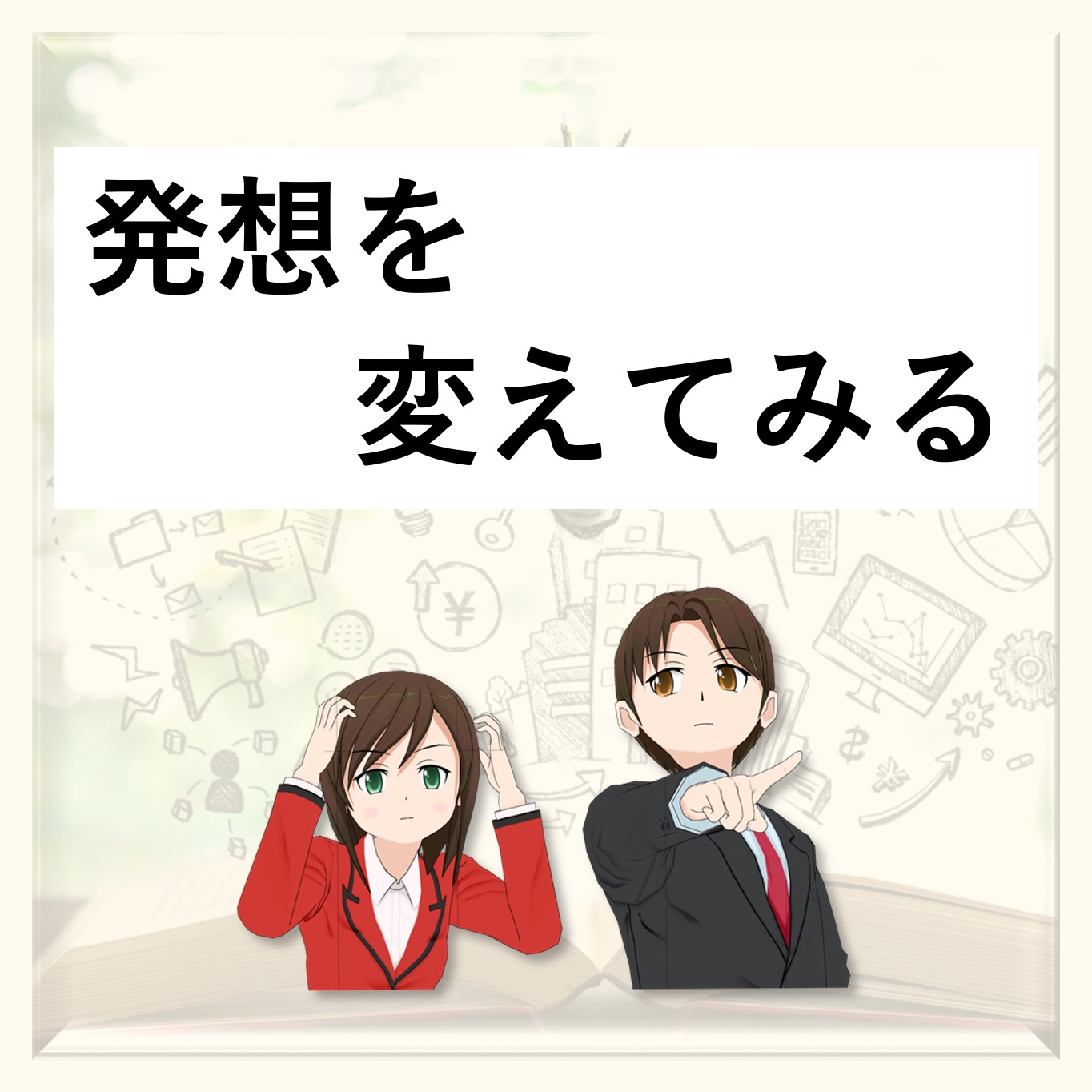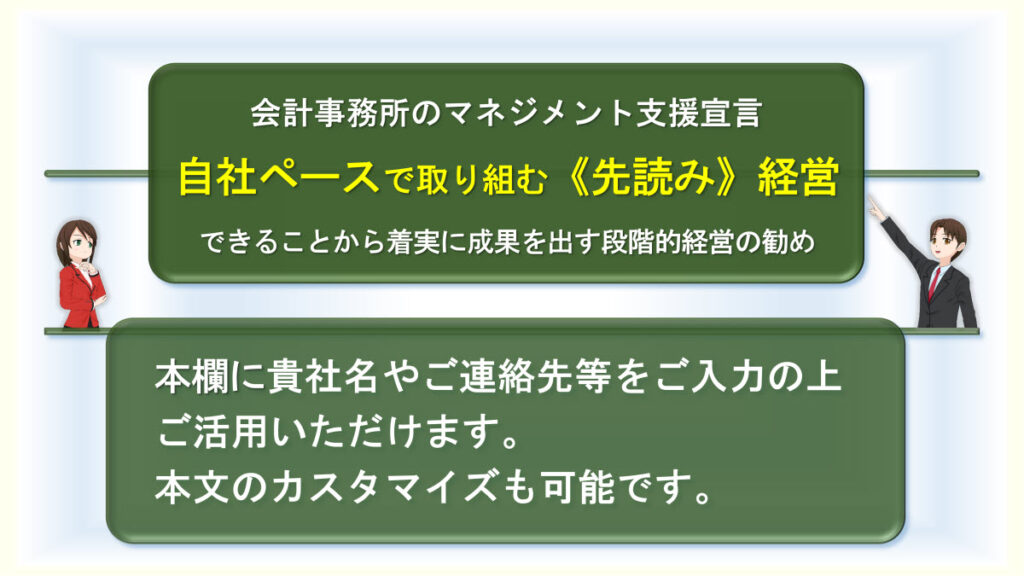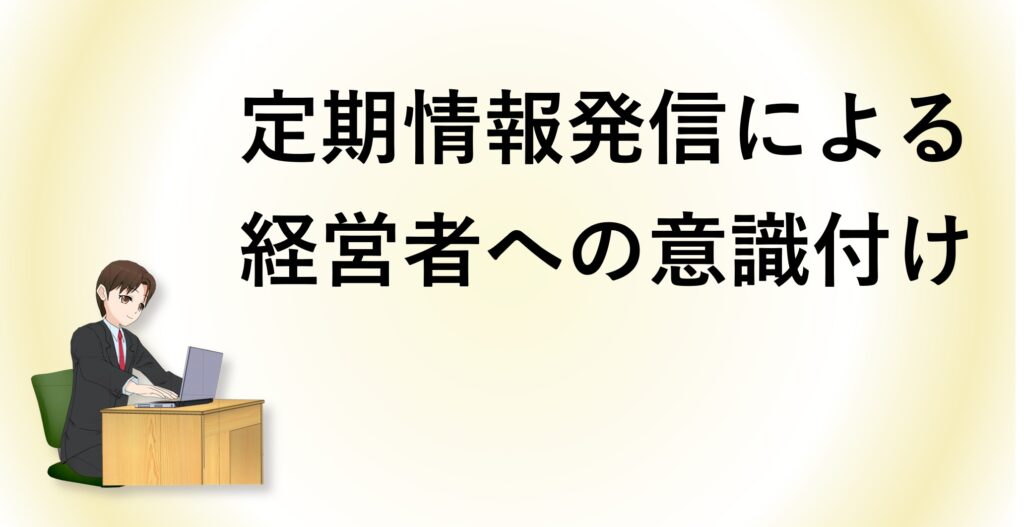医師は病気を治す(治療を促進する)役割を果たします。ただ、最近では予防医学として、健康を守る、あるいは促進する役割を意識する医師も、増えつつあるようです。特に高齢になると、罹病はそのまま《健康寿命の終焉》を意味しかねないからでしょう。
では、会計事務所業界にも《同じこと》が言えるのでしょうか。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.会計事務所が持ち得る3つの機能
会計事務所は、申し上げるまでもなく、決算を通じて《関与先の事業の健康状態が分かる》ポジションに立っています。事業のパワーや経営上の問題は、当然のごとくに《決算結果》にあらわれるからです。
そのため、単に決算を代行するだけではなく、決算という《事業の健康診断》結果を関与先経営者に伝えることが、1つ目の会計事務所の重要な機能と言えるはずです。
それだけで、意欲のある経営者は、健康管理に熱心な人と同様に、『何とかする』ものでしょう。
2.2つ目の機能は付加価値だった?
ところが経営者の行動傾向は、やや古い話になりますが、昭和のオイルショックによる経済高度成長の終焉で変化を始めます。その頃から、勢いのある市場成長を背景に《頑張れば何とかなる》という状況が、徐々に失われて行ったからです。『どうすれば良いか分からない』という経営者が増え始めたわけです。
それを受けて会計事務所業界では、《決算=事業の健康診断書》を手渡すだけではなく、1980年代から経営改善の助言をするMASの隆盛が始まります。
付加価値としてではあっても、経営の助言は会計事務所の重要な2つ目の機能となりました。
3.付加価値的な支援は限界を迎える
ところがその後、平成のデフレ経済(熾烈な価格競争環境)と人口の高齢化の中で、2008(平成20)年には日本の総人口がピークを迎え、その後減少に転じます。
既に経済成長の鈍化で、なかなか失敗を取り戻せなくなっていた市場に、縮小という《新たな事態》が加わったわけです。更に令和になって、企業の《人員不足》が深刻化し、そこへ今度はインフレ転換が始まって、中堅中小企業の経営問題は一層深刻化して来ています。
もちろん、そんな中でも《誕生》し《拡大》する新たな市場も生まれ、事業環境は益々錯綜して来ました。
4.計画的取り組みこそが成果の源泉
そうした中では、《助言》を受けて《頑張ってみる》時にも、経営活動は、最低限でも《計画的》に進めなければならなくなります。問題深刻化の中で、直ぐに解決できる方法が見つけにくくなるばかりか、解決そのものにも時間がかかるため、経営には《かつてなかった程の計画性》が求められるようになるからです。
つまり《助言》が適切でも、計画への意欲や持続的な実践努力がなければ、《どうにもならない》状況に、多くの経営者が追い込まれ始めたということです。しかも、経営者自身の高齢化が進む中で、新しい活動への取り組み意欲も、そう簡単には湧かない状況が慢性化します。
5.経営努力なしには事業は更に悪化
しかも昨今の状況は、昭和や平成とは比べ物にならないほどの《経営判断力や組織牽引力》を求めます。市場は小さくなり、その中で自社市場を広げようとしても、肝心の社内人員が不足し、金融機関の融資条件は厳しくなるとともに、社内の従業員意識にも変化が生まれ、経営トップの号令一下で、たちまち組織が動き出すということにはなりにくいからです。
事業上の問題を解消し、経営力を高め、人材を強化し、取引先や顧客や金融機関の信用を獲得しなければ、もはやニッチもサッチも行きません。そしてそれらの課題は全て一朝一夕には克服できないのです。
6.その中で登場した《第3の機能》
そんな中で、当然の成り行きとして、会計事務所に3つ目の機能として、計画経営(経営管理:数値経営)の支援が加わります。予実管理や経営計画、投資回収計画や資金返済計画に加え、長期間かけて取り組む事業承継計画等が、そこに含まれるのです。
ただ、企業経営者の多くは《計画経営》に興味すら示さないかも知れません。『そんなことに取り組む時間がない』『計画は絵に描いた餅に過ぎない』等の反論の中で、目先の問題に取り組み続けるのです。
ところが、その目先の問題は《中長期的な計画視点》に立たなければ解決しないものがほとんどなのです。
7.企業側の受入れ姿勢は芳しくない
既に申し上げた通り、売れ筋商品の確保でも、資金や人材の調達でも、取引関係の開拓や育成でも、全て時間がかかる話だからです。しかも、商品の開発や資金調達等の中長期的課題でも、『それは先の話』なのではなく、たとえば先々融資を受け得るために今何をすべきかという《目先の課題》なのです。
超長期課題に見える事業承継課題も、今日の現経営者の姿勢が後継者の後継意欲を大きく左右することを、分かっていなければなりません。
それなのになぜ、経営者の多くは、計画経営の《目前課題性》に気付かないのでしょう。
8.提案よりも助言のイメージだから
それは、『計画経営に取り組もう』という会計事務所の勧めが、2つ目の機能のMASのケースのように《助言》に終わるものだと捉えられているからなのかも知れません。つまり『こうすれば解決するよ』『こうした方がいいよ』という助言と同じレベルに、経営者に捉えられがちだということです。
事業状況を改善するだけでも精一杯を超えそうなのに、《計画経営》という《何のためにどうするのかが分かりにくい》新たな取り組みを行うのは至難の業になりかねません。
9.《できる》ことから順に取り組む
そのため、計画経営の提案内容は、まずは対象とする経営者に《今》できて、《先行き》に成果をイメージできる《小さなテーマ》から選び始めるべきでしょう。体系的な予算や計画ではなく、たとえば計画や見通し作りのベース(計算の前提条件)となる《原価の記録》や《商品別の売上管理》や《間接部門の担当毎の経費》等、現状の問題の発掘法や考えるための材料の探し方等、とにもかくにも《少しの努力でできる》ことからスタートするのが、計画経営の入口になるということです。
あるいは、資金繰りに不安が出た時、『今後の収支見通しを立ててみましょう。社長は、その計算のための販売量や価格やコスト等の前提条件を作ってください』等と呼びかけるのです。
10.会計事務所に求められる有料提案
ただし、そんな《入口》から《継続指導》を始めるためには、その支援を《有料にする技術と提案力》が不可欠になります。決算のように《体系的にまとまった仕事》や、金融機関向けの返済計画作成のように《成果が見えやすい業務》だけを有料化するのではなく、《一見、何でもない日常的な業務を合理的に有料化》する技術と姿勢が、会計事務所サイドに求められるということです。
その指導法も、たとえば役員会研修で教えて宿題を出し、次回にそれをチェックする形にしたり、複数の企業に《同じような指導》を、同じような《様式》で実施するなど、可能な限り《指導の負担》を軽減する方法を考える必要も出るかも知れません。
11.第3機能なしに企業の将来はない
第1機能である《決算という名の事業健康診断》が会計事務所の本業であり、第2機能の《MAS》が会計事務所の付加価値だとすれば、第3の機能の《計画経営支援》は、業務有料化をベースとした本格的で継続的な経営指導になると捉えるべきでしょう。
ただし、その経営指導は《事業指導》ではなく《事業活動の管理法の基礎から応用の順次伝授》ですから、企業によって基本が大きく変わるものでもないはずなのです。
もちろん計画経営指導は、会計事務所にとって必須のサービスではないかも知れませんが、今日の中堅中小企業にとっては不可欠なものだと言えます。今、中堅中小企業界は、そんな正念場に立っていると言えるのではないでしょうか。