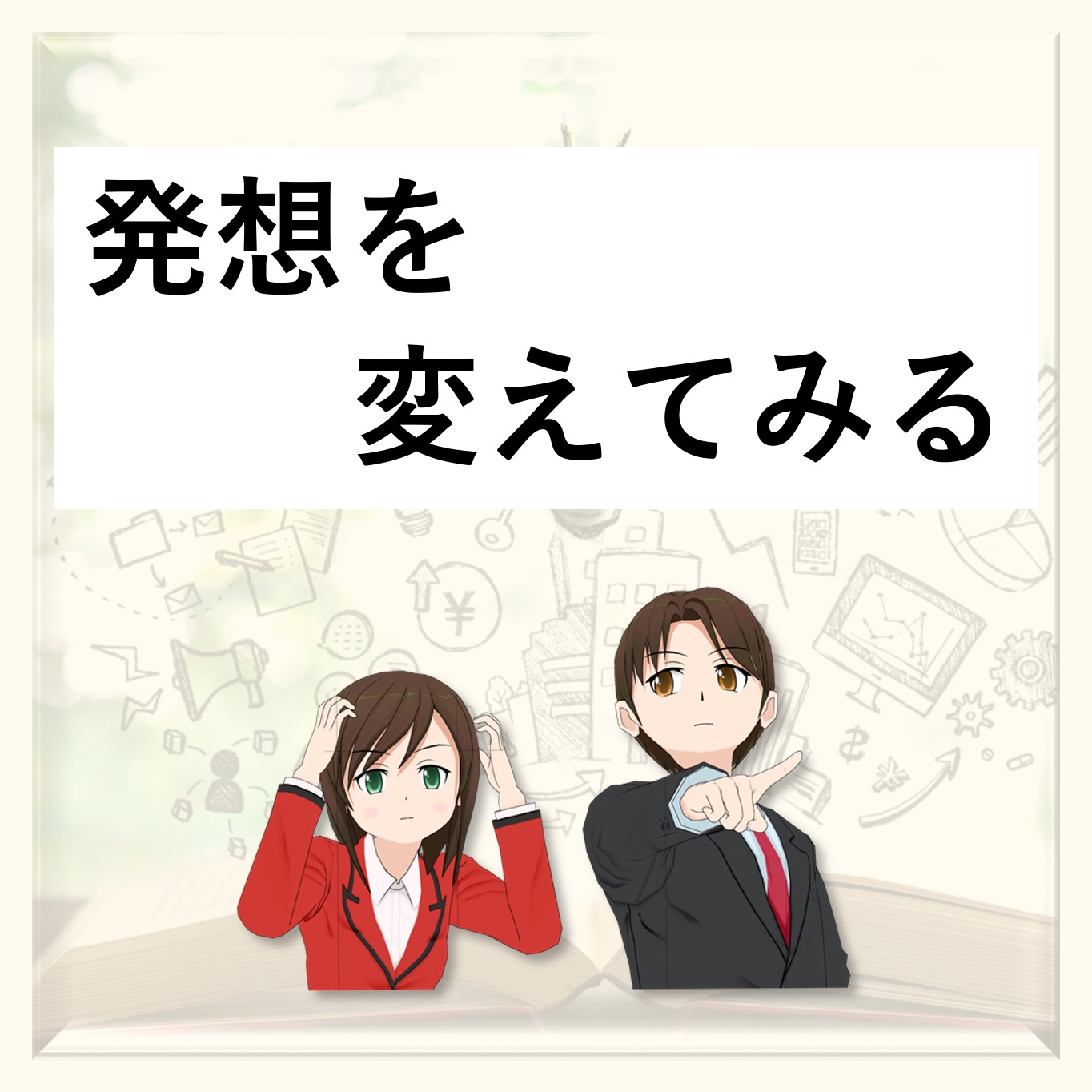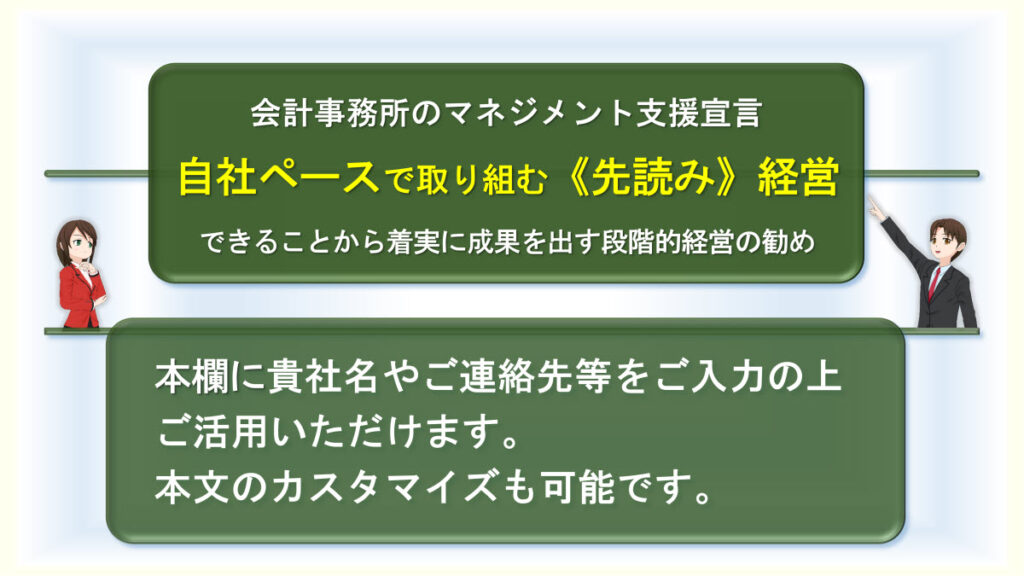経営者との《距離感》は士業ビジネスにとって、これまでも重要かつ微妙なテーマでした。そして《経営者に対して優位な距離感》をとるポジション考察というテーマとなると、一気に難しさが増してしまいます。ところが今、組織で働く現代人の《感性の変化》によって、かつての難題が一気に《解消される機会》が生まれているようなのです。
ご一緒に《確認》しましょう。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.マネジメント理論に無関心だった経営者
マネジメント理論には、一般に《企業戦略》《組織論》《会計学》《ファイナンス》《マーケティング》《生産性:オペレーション》《投資理論》《リスク管理》等、多様なジャンルがあります。ところが、特に中堅中小企業経営者には『そんな勉強は(私には)必要ない』と言われるケースが少なくなかったのではないでしょうか。
それは、中堅中小企業あるいは更に規模の小さい零細企業の経営レベルは《高くない》からなのでしょうか。否、そんな経営者姿勢は、大企業でも同様です。なぜなら、経営学は経営者の本務とは言えないからでしょう。
2.経営者の《本務》とはいったい何なのか?
経営者の本務は、一口に捉えるなら《自社の組織統制》にあります。最近では《ガバナンス》という用語を通じて注目を集め始めた仕事です。ただ、経営者の仕事が《自社統制》にあるのは、多分この世に《組織》が出来て以来《当たり前》のことだったはずです。
そして、多くの経営者は《オーナーとしての立場》や《人柄》あるいは《事業への熟知度》や《先頭を走る主体性》等で、かなり自然に《組織を統制》できていたのです。構成員が自然な形で経営者について行ったということです。
3.組織統制上の無理が少なかった経営者は…
やや《言い方》が不適切になるかも知れませんが、組織統制とは組織内の《専任者=担当者》を自社活動の中に組み込んで《使いこなす》ことに他なりません。指示を与え、その実行を管理し、評価を下すわけです。
そんな統制を比較的容易にできた経営者は、個人差はあっても、同じ姿勢を《社外にも向ける》のです。意識的にであれ、無意識的にであれ、会計事務所をも《一担当者》のごとくに扱いやすいと言うことです。
4.統制者と《業務専任者》との関係ならば…
先生方が、どんなに高度な見識を持っておられても、経営者の意識が『事業の統制者の立場から先生方を捉える』なら、自社の従業員に対するように、『無理を言う』のは当然かも知れません。統制者は『少しでも甘い顔をすれば付け入れられる』ことをよく知っているからです。
それ故、例外は多々あっても、先生方と経営者との関係には《難しい部分》が少なくなかったと、一般的には言えるはずなのです。
5.経営者の《本務遂行》が急に難しくなった
ところが、その《経営者の本務=組織統制》が最近、急に難しくなって来ているのは申し上げるまでもありません。最近、思い出したかのように《ガバナンス=組織統制》が叫ばれているのは、当たり前の統制が難しくなって来ている証拠でしょう。
もちろん、その背景には働き方改革やハラスメント防止法等がありますが、最大の要因は、私たち《現代人》が、経営者の恣意ではなく《合理的》な経営を求めるようになったと捉えられます。自己意識が強くなった現代人は、他者に隷属するのを嫌うのです。今までそうだったと知ると、必要以上に隷属を嫌悪します。必要以上に…。
6.合理的な統制=マネジメント手法等の導入
その際、経営者の恣意ではなく合理的な統制が、《ガラス張りのマネジメント》を意味するのは、申し上げるまでもありません。大きな権力を持つ経営者も、権力を背負って仕事をする公務員と同様に、《法やルール》に従って行動して欲しい、と多くの人が願い始めたということです。
そして公務員の《法やルール》こそが、企業経営上の《マネジメント手法》に当たるのです。
マネジメント手法には、会計やファイナンスのみならず人事問題や生産性を上げる業務学やマーケティング、戦略設計や投資回収理論等、様々な分野があり、そこには《専門家》が存在します。これからの経営者は、少なくとも、そうした専門家から《マネジメント遂行上の支援》を得なければ、事業見識や人柄や意欲だけでは、組織を動かせなくなったということです。
7.経営者自身が深くは意識していなくても…
経営者自身が深くは意識していなくても、社内の担当者にも社外の専門家に対しても《向ける目》が変わって来るのは、今や自然なことなのです。そのため、会計事務所が緊急に取り組むべき課題が出て来ました。
その課題を端的に捉えるなら、先生方が国家資格者として税務上の《適正会計》の担い手であるばかりではなく、実際経験の蓄積等から《決算分析や収支見通し等のシミュレーション計算力》を通じて、経営者の《組織統制》に役に立つという現実を知らしめることに他なりません。
8.なぜ分析や計算力が組織統制に役立つのか
今日的な組織統制には《合理的な基準》が必要だと申し上げました。そして、指示や命令のベースとなる《経営判断》の合理性(=確からしさ)を示すには、客観的な数値を提示するのが最も効果的なのです。
もちろん、客観的な数値を提示しても、先行きそれ自体が現実とかけ離れる場合はあり得ます。しかしそれでも、数値なら、抽象的な言葉よりも《組織内で共有しやすい》ため、その明瞭性が《合理性》を感じさせる基礎を形成するということです。
9.数値を読めない人に対する経営の重要課題
ただ、組織内には数値を読むのが苦手な人もいます。そのため、たとえば《販売量》や《生産量》だけを決めて、それをノルマ化するというマネジメントが、従来、主流だったのでしょう。しかし目標数値だけでは、担当者には、それが合理的なのか無理なのかが分かりません。『事業存続のために不可欠だ』と言われても、ピンと来ません。
そこで、たとえば《年度予算》のような《社内での数値共有の場》が重要になるのです。予算の場では、数値を読むのが苦手な人も《分からない部分を質問》できますし、すぐに分からないことでも《経験》を重ねることで理解を深めることもできます。
年度予算や借入返済計画のみならず、決算分析に関しても、何がどの程度不足(過剰)かを明確にする意味が、ここにあるのです。事業課題を社内で共有するための基礎が出来上がるからです。
10.マネジメントの目的は《完璧性》ではない
マネジメント手法を《勉強》する場合は、その手法の完璧(と言っても60~80点以上?)性が大事になりますが、ビジネス実践の場では、一定の妥当性を持つ方法を構成員の《必要性》や《レベル》で有することの方が重要です。たとえば『予算作りは難しい』のではなく、『自分たちの事情にそって作って守れる予算を作る』ことが大事だということです。
ただし、そのためには《過去の実績の引き延ばし》的な見通し設計ではなく、商品の製造や販売の《上限=製造販売能力》等を意識しながら、コスト等の諸条件をベースにしたシミュレーション計算ができるようにならなければなりません。
超概算でも何通りかの条件設定を行い、最も納得できる計算結果を予算化するという《センス》が必要になるのです。しかも、シミュレーション計算ができるようになれば、期中の計画変更も容易になります。
11.コンサルティングに関しても発想を大転換
以上のように捉えるなら、予算であれ何であれ、企業が理解や修正ができない高レベルのものを会計事務所が提供しても意味がないことが明らかになります。つまり、決算分析や資産税対策等を含む計画経営は、分析結果や完成した計画の提供ではなく、企業レベルに合わせた《シミュレーション技能》の提供だと言えるのです。
計画パッケージの提供よりも、その技能指導の方が難しそうに聞こえるかも知れませんが、その《技能教育》を有料化できるなら、会計事務所が取り組む余地は、大いに高まるのではないでしょうか。ビデオやテキストを有償提供するという手法も出て来ます。
12.初歩的でもシミュレーションができれば…
先行き不透明感が益々濃くなる今後は、中堅中小零細企業にも適切な判断と組織統制を実現する手段が不可欠になると、これまでも申し上げて来ました。それどころか、借入返済計画について、金融機関から『売上が5%ダウンしたらどうなりますか』等と質問されて、大騒ぎしているようでは話になりません。
逆に、たとえ初歩的にでも、シミュレーションができるようになった企業の経営は、恐らく様変わりになって行くでしょう。そこには、経営者のより的確な判断と、判断の合理性を感じて従う組織員の《姿》が見えるからです。
コンサルティングあるいは経営支援は、経営者の組織統制をサポートすることだと捉えるなら、今後の経営支援の方向性も大きく変わりそうですし、企業と士業の双方の経済的な《実り》も、もっと大きくなりそうなのです。