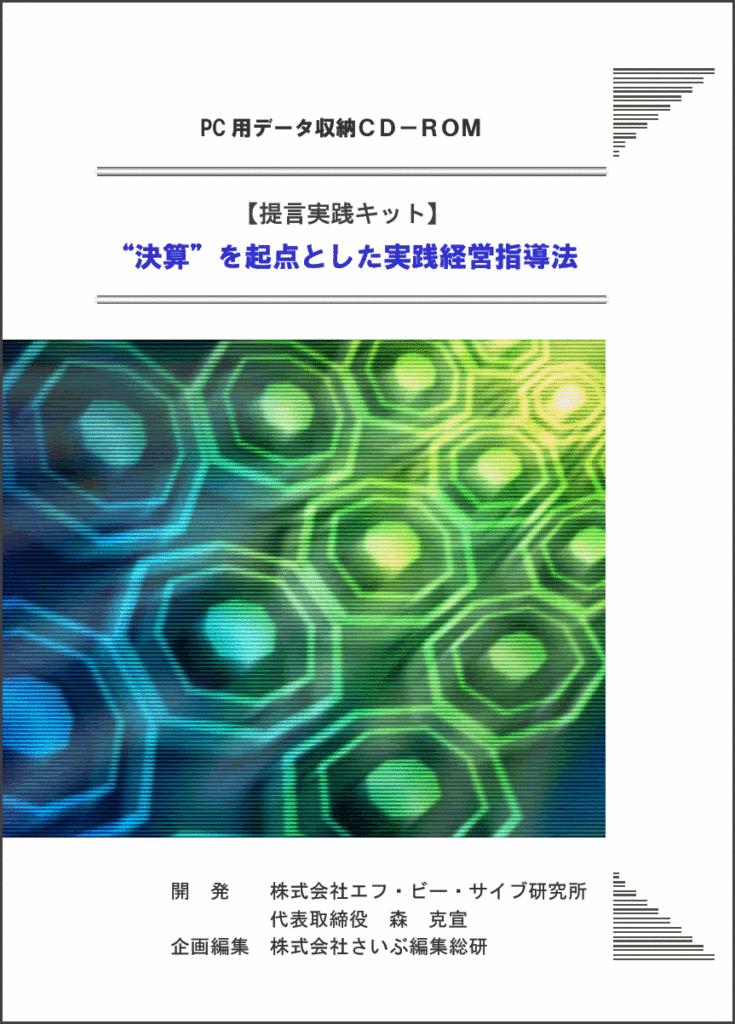企業の決算は『何のために行うか』を、経営者は明確に認識できているでしょうか。その一方で、会計事務所は、どうでしょう。そんな《認識》の深浅が、企業の今後ばかりではなく、会計事務所の先行きにも《大きな影響》を及ぼしそうなのです。
目次
1.決算数値を気にするだけでは不足
企業経営者も、決算のみならず月次試算表が《気になる》のが普通です。なぜなら、そこには当年度あるいは当月の業績結果が出ているからです。ただ、その《気になり方》は問題でしょう。
たとえば、好きなスポーツチームが《今日の試合で勝ったかどうか》が気になる時のように、結果だけが見たいなら、どんなに熱心なファンだったとしても、それは《傍観者(観客)的関心》に過ぎません。試合の経過や選手の活躍の様子を記録で追っても、それだけでは傍観者の域を出られないでしょう。ただの興味や娯楽に過ぎないからです。
2.チームの監督やオーナーならば…
ところが、チームの監督やオーナーなら、同じように《結果》を見、同じように《選手の活躍状況》をチェックしても、決して傍観者には留まりません。なぜなら、選手に《気合》を入れたり、メンバーを入れ替えたり、作戦を変更したりして、次の試合への準備ができるからです。
もし、経営者が《決算や月次試算表》の目的を明確に認識していないなら、そして会計事務所が税務申告用の決算資料をまとめるだけで、それ以上の意欲を抱けないとしたら、この監督やオーナーの感覚が抜け落ちているからかも知れないのです。
3.経営者が決算を重視できない理由
ではなぜ自身の会社の《決算》や《試算表》を前にして、監督やオーナーのようにアグレッシブになれないのでしょうか。それは業績結果を見るだけで『先行き好転のために何かを変えられる』とは思えないからでしょう。
多くの経営者にとって、先行きを変えられるものは《紙切れの上の数値》ではなく《日々の頑張り》なのです。業績に働き掛け得るのは《頑張り実践》であり、決算等はその頑張りを評価する《通知表》に過ぎないとも見えてしまいます。そのため、通知表を分析する時間すら無駄に思えて来るのでしょう。
しかし、そこが《経営上の最も深刻な問題》なのです。
4.従来路線から抜け出せない捉え方
昭和の時代は《がむしゃらに頑張る》ことで、多くの場合成果が出ました。経済全体が、様々な問題を抱えながらも成長していたからですし、《成長》という《基本路線》が、あちこちに敷かれていたからです。
その成長が停滞した平成期には、徐々に《頑張る》ことより《頑張り方》や《頑張る方向》が問題になります。経営には、フットワークよりヘッドワークが求めらるようになります。
そして令和の今、中堅中小企業の多くが《ヘッドワーク》なしには『どう頑張ればよいのか見当もつかない』状況に陥ったと言えそうなのです。
5.活動のキャプテン視点からの卒業
しかし、それは《悲劇》や《行き詰まり》ではなく、現代の中堅中小企業経営者が『ガッツで頑張るぞ、オー!』という意気込みでチーム引っ張る《スポーツチームのキャプテン》の立ち位置から、監督やオーナーの視点に移行すべき時に来ているというだけのことかも知れないのです。
つまり、変わらぬ路線で頑張るのではなく、『自分の《判断》で状況好転への変化を起こせる』ことを思い起こすべき時だということです。経営者は自らの《意思決定》で、事業の路線や体制を変えられるのです。
そして決算書は、その《意思決定》の起点となる《現状》を、つまびらかにしたものだと言えるのです。
6.サポートできる機関は限られる!
ただ、そんな意識転換は想像以上に難しいようです。次々に《試合》に出なければならないキャプテンには考える時間が持てないばかりか、『考えよ』という助言が《日々の努力の邪魔》にさえなるからでしょう。
そのため、どうしても自ら考える前に、《外部からの直接的な指摘や助言》が必要になります。そして今、そんな《具体的な指摘や助言》を、中堅中堅中小企業の経営者に《発信》できるポジションにあるのは、会計事務所と社会保険労務士事務所以外には、見つけにくいのです。しかも、直接的な《業績改善分野》での指摘や助言は会計事務所の独壇場になります。
7.すべきこと、できること、有益性
さて、会計事務所は《何をすべき》なのでしょうか。そして《何ができる》のでしょう。そして、その指摘や助言は、《会計事務所のビジネス》になり得るのでしょうか。
この《すべきこと=役割》と《できること=可能性》と《ビジネス化=支援の有料化》は、全て《同じ発想基盤》から生まれます。
8.起点は気付いたことの投げかけ?
その《発想基盤》とは、難しいこと(たとえば計画経営法や決算分析法)の《それらしい提供》ではなく、会計事務所が今の業績数値の中で《気付いた》ことを、経営者に率直に伝えることに他なりません。
ただ一般的には、決算を経営判断に生かし、業績改善路線を見出すには、財務会計や税務会計ではなく《管理会計》が必要だとされます。そして最低限、社内の活動を商品別や部門別に分け、それぞれの《業績実態》を掴むことから始めなければならないと言われるかも知れません。
9.直接的に目的を追求する方が大事
しかし、管理会計は《事業上の問題把握》を促進し、ヒトとカネの《再配分》を考えやすくするための道具に過ぎないでしょう。税務決算上でも、たとえば『この商品、利益に貢献しているのかなあ』とか、『遊んでいる設備がありそうだ』とか、『これは外注の方が採算が上がるのではないか』等と、気付けるケースがあるはずです。
そんな疑問を会計事務所が持って、経営者に『調べてみてください』と伝えて《データ作り》の指導をするなら、完全な管理会計の仕組みを作らなくても管理会計と同等の成果が得られるはずなのです。
10.中堅中小企業らしい経営改善の姿
本KIZUKIサイトでは、新しいノウハウや技術や方法論ではなく、まさに『今気付けること』を、《役割》や《可能性》や《企業と士業双方のビジネス》に変換する《発想転換の試み》に挑戦し続けて来ました。
その挑戦は、たとえば『管理会計を導入しよう』という体系的な理屈より、『管理会計的発想が実現する成果を一つでも、今のままで獲得しよう』という認識がベースとなっています。
企業も会計事務所も、『少しの視点転換で、困難だと思っていたことが、できるようになる』ということです。そして、それこそが《大がかりな改善》よりも《小さな改善の蓄積》によって、企業の経営力と事業力を《結果》として強化するという《中堅中小企業の実情に最も適合する》経営改善発想なのです。